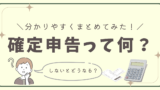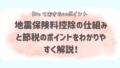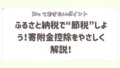こんにちは!
Webライターのまなむです^^
今回は児童手当について気になったことをまとめてみました。
「児童手当って非課税じゃないの?」
「年収制限ってどうやって決まるの?」
実際に子育てしていると、こんな疑問が出てきますよね。
今回は、児童手当の基本から“課税”との関係、そして気になる年収制限についても、わかりやすく解説していこうと思います!
最後までお付き合いいただけたら嬉しいです^^
児童手当は非課税だけど…重要なのは「所得制限」!

児童手当は、子どもがいる家庭に対して支給される国の制度で、『非課税所得』とされています。
つまり、受け取ったお金に対して税金がかかることはありません。
支給額は年齢や人数によって変わりますが、月1万円~1万5,000円程度が一般的です。
ただし、「誰でも満額もらえる」というわけではありません。
じつは、所得制限が設定されていて、一定以上の所得があると支給額が減る、もしくは減額された『特例給付』しかもらえない仕組みです。
非課税って聞くと「じゃあ気にしなくていいや」って思ってしまいがちでしたが、実際は所得の状況で金額が変わるなんて…
知っておかないと損する仕組みですよね!
所得制限と特例給付の仕組み

児童手当の所得制限は、『扶養親族等の数』に応じて限度額が変わります。
たとえば扶養親族が1人なら、所得制限限度額は約875万円(年収で約960万円)ほど。
これを超えると、通常の手当ではなく『特例給付』として月5,000円だけになります。
この所得制限は毎年6月に判定され、その年の所得状況に応じて翌年3月までの支給額が決まるそうです。
私は最初、扶養の数で制限額が変わるのも初耳で、
「うちは何人で計算されるんだろう?」
って混乱しました…。
特例になると一気に手当が減るので、ちょっとした差でも大きな違いになるなあと実感しました。
控除を活用すれば、所得制限を下回れることも

児童手当の所得制限は『課税所得』ではなく、『所得控除前の金額(=扶養控除等を引いた後の金額)』で判断されます。
ここでポイントになるのが、控除の活用です。
たとえば、以下のような控除が影響します。
◎生命保険料控除
◎社会保険料控除
◎医療費控除
◎小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)
◎ひとり親控除 など
これらをしっかり申告しておくことで、所得制限を下回って満額の児童手当を受けられる可能性があります!
所得控除は、税金のための控除だと思っていましたが、児童手当にも影響してるなんて!
節税って、子育て世代にとっては「もらえるお金を守る手段」でもあるんですね。
世帯主の収入がポイント

共働きの場合、「誰の収入で所得制限を判定するのか?」が気になるところです。
児童手当は『恒常的に所得が高い方』の所得をもとに判定されます。
つまり、世帯主でなくても、妻のほうが収入が高ければ、その人の所得が対象となるんだそうです。
判定はあくまで『実質的に家計を支えている人』が基準となります。
そのため、「名義は夫だけど、妻の方がす働いてるから自分が判定される」というケースも珍しくありません。
これ、実は一番意外でした!
私はシングルマザーなので自分の収入が関係してくるのは当然です。
しかし、世の中のご夫婦は「旦那さんが世帯主だから大丈夫」と思い込んでいました。
共働き家庭ほど要チェックのポイントだと思います!
まとめ
児童手当は、毎月自動で振り込まれるからこそ、つい意識が薄くなりがち。
でも、収入や控除の状況次第で金額が減ってしまう可能性がある以上、「自分の家庭がどの位置にいるのか」を知っておくことがとても大事です。
また、確定申告や年末調整のときに控除を漏れなく申告することで、満額の手当をキープできるかもしれません。
将来の教育資金や家計を守るためにも、賢く制度を使っていきたいですね。
私は最初、「どうせ決まった金額でしょ」くらいに思っていました。
でも、調べてみたら意外と繊細な制度だということがわかって…。
ちゃんと知っておくって、すごく大事だなって思いました!
最後までご覧いただきまして、ありがとうございました^^
\合わせて読みたい♪/